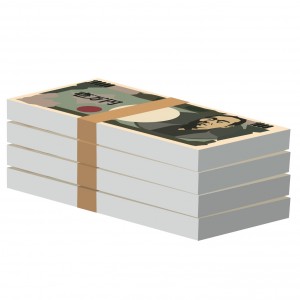相部屋ホームをあらためて考える
以前「有料老人ホームの居室は個室であるべきか問題」という題のブログ記事を挙げたことがあります。2016年の投稿ですので9年前のことになります。
有料老人ホーム設置運営指導指針に「原則個室」が掲げられた平成15年(2003年)以降、事実上「相部屋有料老人ホーム」は設置が困難な状況が続いています。それ以前に届けられたホームは9年前も今も引き続き相部屋ホームとして運営されていますが、首都圏に限って言えば有料老人ホームの相部屋は数%程度(1%くらいかもしれません)です。「プライバシーの尊重」がその大きな理由です。
9年前の投稿ではその数少ない「相部屋ホーム」にも良い点はないのか、相部屋ホームを選ぶときの注意点はどこか、という解説に加え「一定のルール整備の上で相部屋ホームがもう少し柔軟に開設されても良いのではないでしょうか」と締めくくった内容になっています。
さて今回は少し視点を変えて「相部屋ホームの開設規制を緩和することで解決できる問題もあるのでは」というテーマで綴ってみたいと思います。
背景1.人手不足の深刻化
増大を続ける要介護高齢者数に比して、ケア側の人材は常に不足した状況で推移してきた介護業界ですが、これからはこの問題がより深刻化することは避けられません。人口の多い団塊世代が75歳以上の後期高齢者となったのは数年前のことですが、今はまだ、その次の世代でやはり人口の多い団塊ジュニア世代が現役です。介護現場の各拠点では中心的な役割を果たす年代になっていますが、この世代が現役を退く20年後、30年後はどうでしょうか。ちなみに昨年(2024年)の国内出生数はわずか68万人です。
30年後の30歳は60万人台しかいないわけですよね。
少ない人手で複数の高齢者をケアすることを考えれば、個室より、共用部で過ごす時間の多い相部屋の方が「目」と「手」が届きやすく、言葉は不適切かもしれませんが「効率よく」看ることができるとは言えると思います。
また高齢者宅を訪問する在宅介護ヘルパーは高齢化が既に大きな問題になっています。介護の資格を取っても、在宅ではなく施設での勤務を希望する人が多いことで在宅介護の現場では在職者の平均年齢が50歳を超え、60代従事者が4割を占めるとの統計もあります。「施設ではなく家で最期を迎えたい」と思っていても、家に来てくれるヘルパーがいなければそれもかなわなくなる可能性があるということです。
背景2.経済力の低下
団塊世代ジュニア以降の世代は「就職氷河期世代」とも呼ばれ、正社員になることが叶わず、非正規雇用の待遇で働いてきた人たちも少なくありません。預貯金をためることもできず、高齢者となっても年金の未納期間が長かったり未加入だったりで低年金・無年金となるリスクを抱えたこの世代も当然、高齢者になります。彼ら彼女らが在宅で済み続けることができなくなったとき、高額な施設に入居することができるでしょうか。「相部屋でも良いので低額なホームに入りたい」という需要は今よりも確実に増えることは間違いありません。
「施設に入るお金がないからこのまま家にいるよ」という選択肢は要介護独居高齢者の場合、前述のとおり介助のために自宅までヘルパーが来てくれることが成り立つ条件です。取りたくてもこの選択が取れなくなる可能性も考えなくてはなりません。
もちろん、運営側も全個室のホームより相部屋ホームの方が建築費用を低額にできますので、入居者から徴収する月額費用も安価に抑えることができます。
背景3.「人との関わり」の再評価
コロナ禍のときに盛んに言われた「ソーシャルディスタンス」は、確かに高齢者をコロナ罹患から守った側面はあったのかもしれませんが、一方で不要不急の外出をとがめられ、いわば「セルフ軟禁状態」を強いられたことで体力だけでなく気力や生きがいを失うこととなり、また友人、知人、親族とのかかわりが薄れてしまう弊害も生むことになってしまいました。
4人室の個室で、共用部で「会話が成り立つ距離感」を他入居者と保つことの大切さは、近年再評価されているようにも思います。
まとめ
以上の背景を踏まえると、高齢者施設の「相部屋規制」は今後、緩和される方向で検討が進んでいくのではないかと思います。まずは2003年に「原則個室化」がうたわれ、現在は全体の個室率が約80%となった特養(特別養護老人ホーム)で個室率を50%程度まで緩和したり、ホーム単体では全室数のうち3割までは相部屋OK…など部分的に相部屋ホーム設置条件が緩和されるでしょう。
特養に倣い、民間の有料老人ホームでも各自治体ごとに相部屋ホーム数を全体の何割まで、とか各ホームごとの「相部屋率」を○○%まではOKとする、などと条件を付けて相部屋ホーム設置が徐々に認められていくのではないかと思います。
音や匂いを減じる仕切りカーテンの発明とか、IT技術の向上次第では誰と誰が同じ居室になるの良いか「相性をAI診断」なんてこともできるかもしれません。現場でのロボット導入も進むでしょう。
入浴時には血圧や体温を自動で測り、発疹や褥瘡の有無など皮膚状態をセンサーで確認、洗身も洗髪も皮膚や髪質に合わせて適切に実施、洗体後は湯温を確認したうえで浴槽への誘導、入浴後はタオルでの拭き上げ、水分補給から皮膚クリームの塗布…とひと通りの介助をすべてロボットがやってくれる、そんな時代もきっと来るはずです。
私の生きているうちに間に合うと良いのですが(笑)
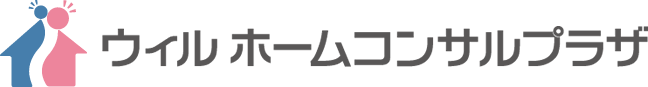

 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム